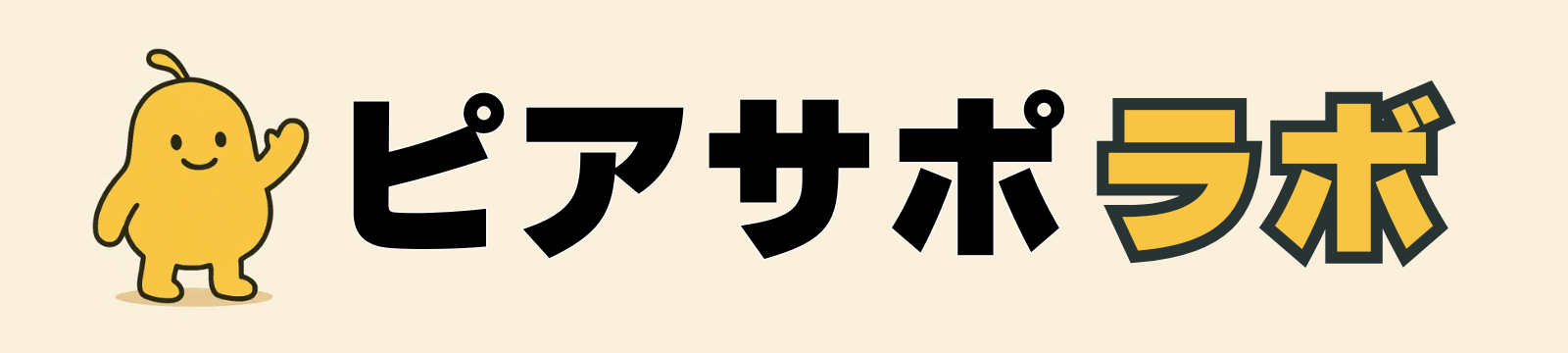ひとりやん
ひとりやん当事者主体!



自己決定の尊重!



(ひとりやん……覚えたての言葉を、理解しないまま使ってないかな……)
福祉の現場や学びの場では、「当事者」にまつわる単語をまるで“お題目”のように毎日耳にします。
しかし、その本当の意味を、私たちはどれだけ深く理解できているでしょうか?
「良かれと思ってした支援が、実は本人の力を奪っていた…?」
「頑張っているのに、なぜか利用者の心に響かない…」
日々の実践の中で、そんな無力感や、自身の関わり方への迷いを抱いたことはありませんか?
この記事では、そんなあなたのための、支援者としての「あり方」を問い直すための方向性をお示ししようと思います。
この記事を読めば、「当事者」という言葉が持つ、歴史的な重みと革新的な思想がわかります。そして、なぜ「当事者主体」が福祉の根幹なのか、その理由が腹落ちし、明日からのあなたの支援は、もっと自信に満ち、もっと希望に溢れたものになるはずです。



たかが単語、されど単語。
組織・チームとして物事に取り組むにあたって、共通言語で会話できているかどうかが大切です。目線合わせのきっかけになれば幸いです!
福祉における「当事者」とは?|「支援される客体」から「人生の主体」へ
福祉の世界で「当事者」という言葉が持つ特別な意味合いと、なぜ「当事者主体」という考え方が基本理念とされるのか。その本質に迫るために、まずは言葉の定義、そしてその背景にある福祉の歴史的なパラダイムシフトを理解することから始めましょう。
日常的な意味との違い|福祉で使われる「当事者」の特別な重み
結論から言えば、福祉の文脈における「当事者」とは、単に「その事柄に直接関係する人」という意味に留まらず、「自らの人生のあり方を、自らの意思で決定する権利を持つ、かけがえのない主体」という、強い権利意識と尊厳のニュアンスを含んだ言葉です。
これは、障害者権利条約や日本の障害者基本法でうたわれている「個人の尊厳」や「自己決定権の尊重」といった基本的人権の考え方が背景にあります。
(参照:厚生労働省 障害者の権利に関する条約)
福祉の世界では、障害や病気、あるいは困難な状況にある人自身を、決して「支援の対象物(客体)」として見るのではなく、その人自身の人生の「主人公(主体)」として捉える、という強い思想が込められているのです。
なぜ「当事者主体」が福祉の基本理念なのか?|その歴史的背景
では、なぜこれほどまでに「当事者主体」が重要視されるようになったのでしょうか。それには、かつての支援のあり方への、深い反省の歴史があります。
かつての専門家主導・パターナリズムへの反省
かつての福祉や医療の世界では、「パターナリズム(父権主義)」という考え方が主流でした。これは、知識や権威を持つ専門家(父)が、本人のためを思い、本人に代わって物事を決定し、指導・管理することが最善である、という考え方です。
このアプローチは、時に本人の意思や願いを無視し、その人らしさや自己決定の機会を奪ってしまうという、大きな問題点を抱えていました。
ノーマライゼーションと当事者主権の思想の広まり
こうした状況への反省から、1960年代以降、デンマークのニルス・エリク・バンク-ミケルセンらによって提唱された「ノーマライゼーション」という思想が世界に広がります。これは、「障害のある人も、ない人と同じように、地域社会の中で普通の生活を送る権利がある」という考え方です。
さらに、1970年代以降には、当事者自身が「私たちのことを、私たち抜きで決めないで(Nothing About Us Without Us)」をスローガンに、自らの権利を主張する「当事者主権」の運動が活発化します。
こうした歴史的な潮流の中で、「支援の主役は専門家ではなく、当事者本人である」という、現在の「当事者主体」の理念が確立されていったのです。
「当事者性」とは?|経験そのものが持つ価値と専門性
「当事者主体」という考え方は、「当事者性(とうじしゃせい)」という言葉にも繋がります。これは、その困難な状況を実際に生きている「当事者の経験」そのものに、他の誰にも代えがたい独自の価値と専門性がある、という考え方です。
例えば、うつ病の苦しみは、どんなに優れた精神科医でも、実際に経験した本人と同じようには理解できません。その経験からくる言葉や知恵は、他のどんな専門知識にも劣らない、あるいはそれ以上に価値のある「専門性」であると捉える。
【重要理念】当事者主体を支える3つのキーワード
「当事者主体」という理念を、日々の支援の中で実践していくためには、その周辺にある重要な3つのキーワードを理解することが不可欠です。
キーワードは3つ。
- 自己決定の尊重
- エンパワメント
- ストレングス視点
これらの言葉は、当事者主体の理念を、より具体的で実践的なレベルに落とし込むための強力な材料となります。
キーワード1:自己決定の尊重|本人が「決める」権利
自己決定の尊重とは、本人の人生に関わる全ての事柄について、最終的な決定権は本人自身にあるという原則です。支援者は、本人が最善の決定を下せるように、専門家として正確な情報を提供したり、複数の選択肢を示したり、あるいは一緒に悩んだりしますが、最後に何を選ぶかを「決める」のは、あくまで当事者本人です。
たとえその選択が、支援者から見て「最善ではない」と思われたとしても、本人が熟慮の末に下した決定であれば、それを尊重し、その決定を支えるのが専門職の役割です。本人が自らの選択に責任を持つ経験そのものが、その人の成長に繋がると考えるからです。
キーワード2:エンパワメント|本人が「力を取り戻す」プロセス
エンパワメント(Empowerment)とは、人が本来持っている力を発揮できない状況に置かれている時に、その人が自らの力(パワー)を取り戻し、自分の人生をコントロールできるようになるプロセスや、そのための支援を指します。
これは、1970年代の公民権運動やフェミニズム運動を背景に生まれた社会福祉の実践理論であり、単なる心理的な「元気付け」ではなく、社会構造的な抑圧から個人を解放するという視点も含まれています。
重要なのは、支援者が外部から力を「与える(give power)」のではない、という点です。当事者の中にもともと存在する、眠っている力を信じ、それが発揮されるような環境を整えたり、自信をつけられるような小さな成功体験を共に喜んだりすること。支援者の役割は、本人が自ら力を取り戻すための「触媒」や「伴走者」となることなのです。
キーワード3:ストレングス視点|本人が元々持つ「強み」に着目する
ストレングス(Strengths)視点とは、人の「できないこと(欠点や課題)」ではなく、「できること(強みや長所、資源)」に意図的に焦点を当てる支援の姿勢です。問題解決モデルが「問題の除去」を目指すのに対し、ストレングスモデルは「強みを活かすこと」で、結果的に問題が気にならなくなったり、乗り越えられたりすることを目指します。
どんなに困難な状況にある人でも、必ずその人ならではの強み(例:ユーモアがある、粘り強い、絵が上手い、人に優しいなど)や、利用できる社会資源(例:協力的な家族、趣味のサークルなど)を持っています。その「強み」を本人と共に発見し、それを活用して目標を達成していく。このアプローチは、本人の自己肯定感を高め、エンパワメントを力強く促進します。
【具体的な活動】当事者主体の理念から生まれたアプローチ
では、「当事者主体」という理念は、現実の支援現場で、どのような具体的な活動として形になっているのでしょうか。ここでは、その代表的なアプローチを3つご紹介します。
当事者研究とは?|自らの経験を、仲間と共に研究する
当事者研究とは、自分自身が抱える困難や苦労(生きづらさ)について、他の誰かに分析してもらうのではなく、自分自身が「研究者」となって、同じような経験を持つ仲間と共に、そのメカニズムや対処法を研究していく活動です。
少し長くてわかりにくいと思いますので、キーワードで押さえておきましょう。
- 研究テーマ:自分自身の困難・苦労・生きづらさ
- 研究対象:他の専門家ではなく、自分自身(=研究者)
- 研究の目的:苦労のメカニズムや、独自の対処法を発見すること
当事者研究の基本的なやり方と目的
当事者研究は、通常、数人のグループで行われます。
一人が自分の苦労(例:「なぜ私は、人前で話すと頭が真っ白になるのか?」)を発表し、他のメンバーはそれを興味深く聞き、「自分の場合はこうだった」「こういう見方もできるのでは?」と、それぞれの経験を持ち寄って、一緒に考察を深めていきます。
ここでの目的は、苦労を「治す」ことではありません。
むしろ、自分の苦労にユニークな名前をつけたり(例:「頭真っ白病」)、そのメカニズムを解明したりすることで、苦労との付き合い方を見つけ、それを笑いやユーモアに変えていくことにあります。
べてるの家の実践事例
この当事者研究は、北海道浦河町にある精神障害のある人の地域活動拠点「べてるの家」で生まれた、世界的に有名な実践です。
「幻覚&妄송大会」など、ユニークでユーモアあふれる活動は、多くの専門家や当事者に衝撃とインスピレーションを与え続けています。
ピアサポートとは?|同じ経験を持つ仲間による支え合い
ピアサポート(Peer Support)とは、同じような立場や経験をした「仲間(ピア)」同士が、その経験を活かして、お互いに支え合う活動のことです。


専門家には打ち明けにくい本音を語り合えたり、先輩当事者の乗り越え方がロールモデルになったりと、専門職による支援とは異なる、ユニークでパワフルな効果が期待されています。
近年では、このピアサポートを担う人材を養成する「ピアサポーター養成研修」も制度化され、彼らを事業所に配置することで報酬が加算される「ピアサポート体制加算」が創設されるなど、福祉の正式な支援の一つとして位置づけられています。
当事者会・自助グループ|安心して語り合える「居場所」
当事者会や自助グループは、同じ悩みを持つ人々が、自主的に集まり、体験や想いを分かち合うための「居場所」です。
「言いっぱなし・聞きっぱなし」などのルールに守られた安全な場で語り合うことで、孤立感を和らげ、「一人じゃない」という安心感を得ることができます。これもまた、当事者主体の理念が草の根で実践されている、最も基本的な形の一つです。
(※当事者会については、こちらの記事で詳しく解説しています。)
【支援者の役割】当事者主体を実践するために、専門職に何ができるか
「当事者が主体なら、専門職である私たちは、一体何をすればいいのか?」
――これは、当事者主体に関する理念を学んだすべての支援者が直面する、最も重要な問いではないでしょうか。
当事者主体は、決して支援者の無力さを意味するものではありません。むしろ、より高度で、本質的な役割への変化を私たちに求めているのです。
役割の変化|「指導者」から「伴走するパートナー」へ
支援者の役割は、答えを知っていて、正しい道へと「指導するリーダー」から、当事者の横に並んで、その人が自分の道を見つける旅に「伴走するパートナー」へと変化します。
私たちは、本人の前を歩くのでも、後ろから押すのでもなく、ただ隣にいて、時に地図を見せ、時に水筒を差し出し、時に一緒に道に迷いながら、その人自身のペースで歩むのを見守る存在になるのです。
求められるスキル|傾聴、共感、そして「待つ」勇気
この新しい役割を果たすために、私たちに求められるスキルも変わります。知識や技術を教える能力以上に、相手の話に深く耳を傾ける「傾聴」のスキル、その感情に寄り添う「共感」のスキルが重要になります。
そして何より、本人が自ら考え、気づき、行動するまで、焦らずに「待つ」ことができる勇気と忍耐力が、専門家としての度量を試されるのです。
専門知識をどう活かすか|本人が選択するための「情報提供」
では、私たちが持つ専門知識は不要になるのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。その使い方が変わるのです。かつてのように、その知識で本人を「指導」するのではなく、本人が自己決定するための「判断材料」として、分かりやすく提供するのです。
「この問題に対しては、A、B、Cという選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットはこうです。あなたはどうしたいですか?」
このように、専門知識を、本人が主体的に選ぶための「情報のビュッフェ」として差し出す。これが、これからの専門職の知的な役割です。
「良かれと思って」の罠|支援者が陥りがちな落とし穴
最後に、私たちが最も気をつけなければならない罠は、「良かれと思って」という善意の暴走です。本人のためを思うあまり、先回りして問題を解決してしまったり、本人の言葉を遮って「要するにこういうことですよね」と解釈してしまったり……。
常に自問自答する必要があります。「この支援は、本当に本人の『ため』になっているのか、それとも、自分の『不安』を解消したいだけではないのか?」と。その自省こそが、私たちを、より謙虚で、より優れた支援者へと成長させてくれるのです。
まとめ
この記事では、福祉の現場における「当事者」という言葉の深い意味について、その背景にある理念から、具体的な活動、そして私たち支援者の役割までを体系的に解説してきました。
「当事者主体」が、単なるスローガンではなく、先人たちの闘いと、深い人間信頼の上に成り立つ、力強い哲学であることがお分かりいただけたかと思います。
最後に、明日からのあなたの実践を支える、この記事の核心的なポイントを振り返りましょう。
- 当事者は「人生の主人公」
福祉における「当事者」とは、単にサービスを受ける客体ではなく、自らの人生のあり方を自ら決定する、かけがえのない主体です。 - 支援の目的は「エンパワメント」
私たちの役割は、問題を解決してあげることではなく、当事者が本来持つ力(ストレングス)に光を当て、自らの力で人生を取り戻していくプロセス(エンパワメント)を、伴走者として支えることです。 - 理念は活動となって息づく
当事者研究やピアサポートといった活動は、まさに当事者主体の理念が具体化したものです。そこでは、当事者の「経験」こそが、最も価値ある専門性となります。 - 支援者は「対等なパートナー」
これからの専門職に求められるのは、一方的に指導するのではなく、当事者の自己決定を尊重し、対等なパートナーとして、共に悩み、共に考える姿勢です。
「当事者のことは、当事者が一番よく知っている」
この当たり前で、しかし、ともすれば忘れがちな真実に立ち返ること。
それが、私たちの支援を、より深く、より豊かなものにするための、すべての出発点なのかもしれません。
今日の学びが、あなたの支援者としての哲学を、そして利用者との関係性を、より良い方向へと導く一助となることを、心から願っています。
参考文献・出典元リスト
本記事で解説した福祉の理念や活動は、多くの先人たちの実践と研究によって築かれてきました。より深く学びたい方は、以下の情報源もご参照ください。
- べてるの家
当事者研究の発祥の地である、北海道浦河町の精神障害のある人の地域活動拠点。そのユニークな理念と実践は、書籍や映像作品として数多く紹介されています。
(参照:社会福祉法人浦河べてるの家 公式サイト) - 厚生労働省「こころの情報サイト」
国の公式なメンタルヘルス情報サイト。リカバリーやエンパワメント、ピアサポートといった、基本的な概念についての解説が掲載されています。
(参照:厚生労働省公式サイト) - 関連学会・研究会
「日本当事者研究ネットワーク」や、各種福祉系学会では、最新の研究成果や実践報告に触れることができます。専門職としての学びを深めたい方におすすめです。