「令和6年度の報酬改定で、ピアサポート体制加算はどう変わった?」
「うちの事業所(B型・グループホーム)でも、この加算は算定できるのだろうか?」
「ピアサポーターとして配置する職員には、どんな研修が必要なの?」
障害福祉サービスの事業所を運営する中で、今、あなたもこのような実務的な疑問をお持ちではないでしょうか。
ピアサポート体制加算は、利用者支援の質を高めると同時に、事業所の収益を改善する上で非常に重要な加算です。
しかし、その算定要件は複雑で、報酬改定のたびに内容を正確に把握するのは容易ではありません。
この記事では、令和6年度の最新情報に基づき、ピアサポート体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件から、対象となるサービス種別、ピアサポーターに求められる研修要件、そして実務で必要な記録まで、あなたが知りたい情報のすべてを、どこよりも分かりやすく、体系的に解説します。

【令和6年度報酬改定】ピアサポート体制加算の主な変更点まとめ
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定は、ピアサポートの更なる推進を明確に打ち出しました。ここではまず、今回の改定における最も重要な変更点を把握し、その背景にある国の意図を読み解いていきましょう。
結論|対象サービスの拡大と、新区分「ピアサポート体制加算(Ⅱ)」の創設
今回の改定における最大のポイントは、加算の対象となるサービス種別が大幅に拡大されたこと、そして、より専門性の高いピアサポーターの配置を評価する新区分「ピアサポート体制加算(Ⅱ)」が創設されたことの2点に集約されます。
これにより、これまで以上に多くの事業所が加算を検討できるようになるとともに、ピアサポーターの専門性やキャリアパスを、より明確に評価する体制が整えられました。
変更点を一覧で確認|新旧比較表
具体的に何がどう変わったのか、報酬改定の前後で比較してみましょう。
| 項目 | 改定前(~令和5年度) | 改定後(令和6年度~) |
|---|---|---|
| 加算の区分 | ピアサポート体制加算 のみ | ピアサポート体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分に |
| 対象サービス | 自立生活援助、就労定着支援など4サービス | 就労継続支援A型・B型、共同生活援助(GH)などが追加され、8サービスに拡大 |
| ピアサポーターの要件 | 基礎的な研修の修了 | (Ⅰ):基礎研修の修了 (Ⅱ):専門研修の修了 + 実務経験 |
このように、対象範囲の拡大と、ピアサポーターの専門性に応じた評価の細分化が行われたのが、今回の改定の大きな特徴です。
今回の改定の背景と目的|ピアサポートのさらなる推進
国がこのような改定を行った背景には、ピアサポートの有効性への高い評価が挙げられます。
専門職による支援とは異なる、同じ悩みや経験を持つ「仲間(ピア)」だからこそできる寄り添いや、ロールモデルの提示が、利用者の自己決定や意欲向上に大きな効果をもたらすことが、多くの実践で示されてきました。
今回の改定は、このピアサポートを一部の先進的な取り組みに留めるのではなく、障害福祉サービスの標準的な支援体制の一つとして、より多くの事業所に導入を促し、その質を向上させていくという、国の明確な意思の表れと言えるでしょう。
ピアサポート体制加算とは?|制度の基本と(Ⅰ)(Ⅱ)の違い
変更点を把握したところで、改めて「ピアサポート体制加算」そのものの基本的な考え方と、新設された(Ⅰ)・(Ⅱ)の区分の違いについて、正確に理解しておきましょう。
制度の目的|同じ障害のある人の経験を活かした支援の評価
ピアサポート体制加算とは、一言で言えば、障害のある当事者としての経験を活かして他の利用者への相談や助言を行う「ピアサポーター」を事業所に配置し、その支援体制を整備していることを評価するための報酬加算です。
ピアサポート、つまり「仲間による支え合い」を制度として評価し、その導入を促進することで、利用者一人ひとりの課題解決や地域生活への移行、就労意欲の向上などを後押しすることを目的としています。
ピアサポート体制加算(Ⅰ)とは?|ピアサポーターによる支援体制の評価
ピアサポート体制加算(Ⅰ)は、ピアサポートの基本的な体制を評価する加算です。後述する「基礎研修」を修了したピアサポーターを配置し、そのピアサポーターが利用者への相談・助言を行ったり、個別支援計画の作成会議に参加したりする体制が整えられている場合に算定できます。
これは、事業所内にピアサポートという新しい支援の視点を取り入れる、最初のステップと位置づけられます。
ピアサポート体制加算(Ⅱ)とは?|専門性を有するピアサポーターの配置評価
ピアサポート体制加算(Ⅱ)は、令和6年度改定で新設された、より上位の加算です。基礎研修に加えて「専門研修」を修了し、かつ一定期間の実務経験を持つ、より専門性の高いピアサポーターを配置している場合に算定できます。
これは、単にピアサポーターがいるだけでなく、その専門性を活かして、事業所全体の支援の質の向上や、他の職員への指導・助言といった、より高度な役割を担う体制を評価するものです。
加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の主な違いを比較表で整理
両者の違いは、主にピアサポーターに求められる要件と、得られる単位数にあります。
| 項目 | ピアサポート体制加算(Ⅰ) | ピアサポート体制加算(Ⅱ) |
|---|---|---|
| ピアサポーターの要件 | ・障害者としての経験 ・基礎研修の修了 | ・障害者としての経験 ・基礎研修 + 専門研修の修了 ・1年以上の実務経験 |
| 単位数(例:就労継続支援B型) | 100単位/月 | 125単位/月 |
| 位置づけ | ピアサポートの基本的な体制整備 | 専門性を活かした、より高度な体制整備 |
【サービス種別ごと】算定要件と単位数の一覧
ピアサポート体制加算は、全ての障害福祉サービスで算定できるわけではありません。ここでは、令和6年度改定後の対象サービスと、それぞれの単位数を一覧でご紹介します。ご自身の事業所が該当するか、ご確認ください。
(注:単位数は加算(Ⅰ)のものです。(Ⅱ)は後述します)
| 対象サービス種別 | 単位数 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 100単位/月 |
| 就労継続支援(A型・B型) | 100単位/月 |
| 就労定着支援 | 100単位/月 |
| 自立生活援助 | 100単位/月 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 100単位/月 |
| 地域移行支援 | 500単位/月 |
| 地域定着支援 | 350単位/月 |
| 自立訓練(生活訓練) | 100単位/月 |
※加算(Ⅱ)は、上記の(Ⅰ)の単位数にさらに25単位が上乗せされます(地域移行支援、地域定着支援を除く)。
(参照:厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について)
【最重要】「ピアサポーター」として認められるための人員要件
この加算を算定できるか否かの最大の鍵は、「ピアサポーター」として認められる職員を確保・配置できるかどうかにかかっています。ここでは、その具体的な要件を詳しく見ていきましょう。
共通の要件|障害者としての経験と、事業所の雇用形態
まず、加算(Ⅰ)(Ⅱ)に共通する大前提として、ピアサポーターは以下の要件を満たす必要があります。
- 障害者であること:支援の対象となる利用者と、同様の障害や疾病の経験を持つ当事者であること。
- 事業所に雇用されていること:当該事業所の従業者として、雇用契約を結んでいる必要があります。
加算(Ⅰ)で求められる研修要件|基礎研修の修了
ピアサポート体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ピアサポーターは、都道府県や指定都市が実施する「ピアサポーター養成研修(基礎研修)」を修了している必要があります。この研修は、ピアサポートの基本的な理念や倫理、傾聴や対話の技術などを学ぶものです。
加算(Ⅱ)で求められる研修要件|専門研修の修了と実務経験
より上位の加算(Ⅱ)を算定するには、さらに厳しい要件が課せられます。
- 研修要件:基礎研修に加え、より高度な技術や、他の職員へのスーパービジョン(指導・助言)の方法などを学ぶ「ピアサポーター養成研修(専門研修)」を修了していること。
- 実務経験要件:ピアサポーターとしての支援提供の経験が、1年以上あること。
これらの要件は、ピアサポーターが単なる「相談相手」に留まらず、専門性を持った支援者として機能することを求めています。
ピアサポーター養成研修はどこで受けられる?|実施団体と探し方
ピアサポーター養成研修は、各都道府県や指定都市、あるいはそれらが指定した民間の研修機関によって実施されています。実施時期や回数は限られているため、計画的な受講が必要です。
研修情報を探すには、まずはお住まいの都道府県の「障害福祉課」などの担当部署のウェブサイトを確認するのが第一歩です。
【実務編】加算算定のために事業所が行うべきこと
人員要件を満たしたら、次は事業所として、加算を算定し、適切に運用するための体制を整える必要があります。
ピアサポーターの役割と業務内容の明確化
まず、配置するピアサポーターが事業所内でどのような役割を担い、どのような業務を行うのかを、就業規則や職務分掌表などで明確に定めておく必要があります。例えば、以下のような業務が考えられます。
- 利用者との定期的・個別的な面談(相談・助言)
- 個別支援計画の作成に関する会議への参加と、当事者視点からの意見表明
- 職員会議などでの、他の職員への情報共有や助言
個別支援計画への位置付けと、支援の記録
ピアサポートは、サービス管理責任者(サビ管)が作成する「個別支援計画書」の中に、具体的な支援内容として明確に位置づける必要があります。「ピアサポーターによる月1回の面談を実施し、就労意欲の向上を図る」といったように、支援の目標と内容を記載します。
そして、計画に基づいて実施した支援については、日々の業務日誌や支援記録に、いつ、誰が、誰に対し、どのような支援を行ったかを具体的に記録しておくことが、実地指導(行政による監査)への備えとして不可欠です。
行政への体制届の提出と、報酬請求(レセプト)
加算の算定を開始する前には、指定権者である都道府県や市町村に対し、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(体制届)」を提出する必要があります。この届出書に、ピアサポート体制加算を算定する旨を記載し、ピアサポーターの研修修了証の写しなどの添付書類と共に提出します。
届出が受理されれば、翌月(または翌々月)から、国保連に提出する報酬請求明細書(レセプト)に、該当する加算項目を算定して請求することが可能となります。
ピアサポート体制加算に関するQ&A
ここでは、現場でよく聞かれる疑問について、厚生労働省のQ&Aなどを基にお答えします。
Q. ピアサポーターは、他の職務と兼務できますか?
A. はい、常勤・非常勤を問わず、他の職務との兼務は可能です。例えば、職業指導員として働きながら、ピアサポーターとしての役割を担うことができます。ただし、ピアサポーターとしての勤務時間を明確に確保し、その業務に支障がないことが前提となります。
Q. 複数のピアサポーターを配置した場合、加算はどうなりますか?
A. ピアサポーターを複数名配置した場合でも、加算は事業所に対する評価であるため、算定額は変わりません。例えば、要件を満たすピアサポーターが2名いても、加算が2倍になるわけではありません。
Q. 利用者への支援は、具体的に何を記録すれば良いですか?
A. 以下の内容を、客観的な事実として具体的に記録することが望ましいです。
- 実施日時:〇年〇月〇日 〇時~〇時
- 実施場所:相談室など
- 対応職員:ピアサポーター 〇〇
- 対象利用者:△△様
- 相談内容の要旨:利用者からどのような相談があったか
- 提供した助言・支援の内容:ピアサポーターとして、自身の経験を踏まえてどのような助言を行ったか
- 今後の課題・引継ぎ事項:次回の面談に向けた課題や、他の職員と共有すべき情報など
まとめ
この記事では、令和6年度の最新情報に基づき、「ピアサポート体制加算」について、その概要から具体的な算定要件、実務上のポイントまでを網羅的に解説してきました。
この加算が、事業所の経営と支援の質を向上させるための、いかに重要なツールであるかをご理解いただけたかと思います。
最後に、この複雑な制度を理解するための核心的なポイントを振り返りましょう。
- 令和6年度改定のポイント
加算の対象サービスが拡大され、より専門性の高いピアサポーターの配置を評価する「ピアサポート体制加算(Ⅱ)」が新設されたことが最大の変更点です。 - 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
(Ⅰ)はピアサポーターによる支援体制を評価する基本的な加算、(Ⅱ)は専門研修を修了したピアサポーターを配置した場合に算定できる、より上位の加算です。 - 対象サービス別の要件
算定できるサービス種別は限定されており、それぞれで単位数や要件が異なります。自事業所が対象かどうかを正確に確認することが第一歩です。 - ピアサポーターの要件
加算の鍵を握るのは、ピアサポーター自身が指定の「基礎研修」や「専門研修」を修了しているかどうかです。適切な人材の確保と育成が不可欠です。 - 計画と記録の重要性
加算を算定するためには、個別支援計画への位置付けや、日々の支援内容の具体的な記録が必須となります。
ピアサポート体制加算は、単なる収益向上の手段ではありません。
それは、障害のある当事者の「経験」そのものを、専門的な「価値」として認め、利用者支援の新たな力へと変えていく、非常に意義深い制度です。
この記事が、あなたの事業所におけるピアサポート導入の、そして、より質の高い支援体制構築の、確かな一助となることを心から願っています。
参考文献・出典元リスト
この記事で解説した報酬加算に関する情報は、厚生労働省が発表する公式の資料に基づいています。制度の解釈や運用にあたっては、必ず以下の一次情報をご確認ください。
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」
今回の報酬改定に関する全ての公式資料(概要、告示、通知、Q&Aなど)が掲載されています。
(参照:厚生労働省公式サイト) - WAM NET(ワムネット)
独立行政法人福祉医療機構が運営する、福祉・保健・医療の総合情報サイト。報酬改定に関する情報や、行政通知などを検索することができます。
(参照:WAM NET公式サイト) - お住まいの都道府県・指定都市の障害福祉担当部署
ピアサポーター養成研修の実施情報や、体制届の様式など、地域ごとの具体的な情報については、各自治体の公式サイトで確認するのが最も確実です。
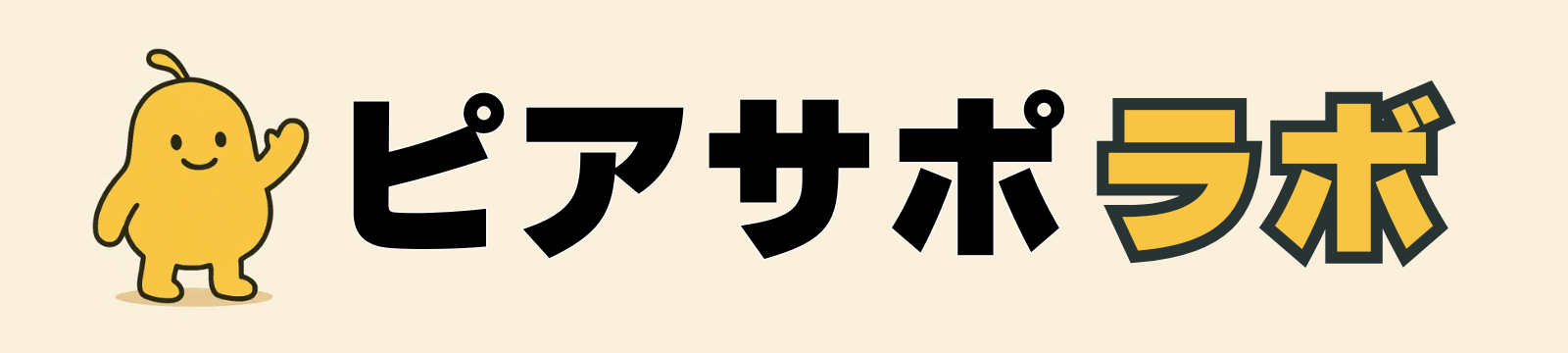



とは?目的・事例・探し方を知ろう!|一人じゃないと思える場があります-300x169.jpg)



