 ひとりやん
ひとりやん障害者手帳の1級って、具体的にどんな状態のこと?



1級だと、どんな支援やサービスが受けられるんだろう?



仕事を見つけるためのサポートもあるのかな……?
障害者手帳の中でも、最も等級の高い「1級」。
その対象となる方やご家族にとって、受けられる支援の全体像を正確に把握することは、生活の質を向上させ、将来の安心に繋がる、非常に重要なことです。



ご安心ください。
この記事では、そんなあなたの疑問や不安に、一つひとつ丁寧にお答えします!
障害者手帳1級の正確な定義から、日々の生活やお金の面で受けられるメリット、そして「働く」という未来を支える就労支援サービスまで、この記事一本で、あなたが知りたい情報のすべてがわかります。
この記事を読み終える頃には、利用できる制度への理解が深まり、次の具体的な一歩を踏み出すための、確かな知識と自信が手に入っているはず。
障害者手帳とは?|3つの種類と基本的な役割
障害者手帳の具体的な等級に触れる前に、まずはその基本についておさらいしましょう。手帳の種類と、それが持つ役割を理解することが、制度全体を把握するための第一歩となります。
障害のある方のための「証明書」
障害者手帳とは、一言で言えば、心身に一定の障害があることを公的に証明するための証明書です。この手帳を所持していることで、後述する様々な福祉サービスや支援、割引制度などをスムーズに利用できるようになります。
これは、障害のある方が社会生活を送る上での様々なバリア(障壁)を取り除き、その人らしい自立した生活を支援するための、大切なパスポートのような役割を果たします。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の違い
日本の障害者手帳は、対象となる障害の種類によって、主に以下の3つに分けられます。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 交付主体 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由(手足や体幹の障害)、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器など)といった、身体機能の永続的な障害 | 都道府県、指定都市、中核市 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など、一定程度の精神障害の状態にあること | 都道府県、指定都市 |
| 療育手帳 | 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された場合 | 都道府県、指定都市 (※法律ではなく通知に基づく制度のため、名称が「愛の手帳」など自治体によって異なる) |
自分がどの手帳の対象となるか、あるいは複数の手帳を取得できるかなどは、医師や専門機関との相談を通じて判断されます。
障害者手帳「1級」の定義とは?|身体・精神・療育別に解説
それでは、本題である「1級」の定義について見ていきましょう。1級は、いずれの手帳においても最も障害の程度が重い等級を指しますが、その基準は手帳の種類によって異なります。
身体障害者手帳1級の基準と対象例
身体障害者手帳における1級は、身体の機能障害が極めて重く、日常生活が著しく制限される状態と定義されます。具体的には、以下のような例が挙げられます。
- 両眼の視力の和が0.01以下のもの(全盲)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
- 両上肢の機能を全廃したもの
- 両下肢の機能を全廃したもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
これはあくまで一例であり、複数の障害を総合して1級と認定される場合もあります。
(参照:厚生労働省 障害者手帳について)
精神障害者保健福祉手帳1級の基準と対象例
精神障害者保健福祉手帳における1級は、精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものと定義されています。これは、他者の援助を受けなければ、食事や身の回りの処理など、ほとんどのことができない状態を指します。
対象となる疾患には、統合失調症、うつ病や双極性障害といった気分障害、てんかん、薬物関連障害、高次脳機能障害、そして発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)が含まれます。病名で決まるのではなく、それによって生じる生活能力の障害の程度で総合的に判断されます。
(参照:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について)
療育手帳(愛の手帳など)の最重度(1級相当)の基準
療育手帳は、法律ではなく国の通知に基づいて各自治体が制度を設けているため、等級の区分や名称が異なります。多くの自治体では、障害の程度を「最重度」「重度」「中度」「軽度」などに分けており、この「最重度」が、他の手帳の1級に相当すると考えられます。
例えば、東京都の「愛の手帳」では「1度」が最重度にあたり、知能指数(IQ)がおおむね19以下で、食事、排泄、着脱衣、身の回りの危険回避などの日常生活において、常時個別の援助が必要となる状態とされています。
(参照:東京都心身障害者福祉センター 愛の手帳について 愛の手帳Q&A)
【一覧】障害者手帳1級で受けられる支援・サービスまとめ
障害者手帳1級を所持していることで、日常生活から経済面、そして就労に至るまで、様々な支援を受けることができます。まずは、その全体像を一覧できる表で確認してみましょう。各項目の詳細については、この後じっくりと解説していきます。
| 支援の分野 | 主なサービス・制度の例 |
|---|---|
| 日常生活の支援 | ・交通機関(JR、バス、航空券等)の運賃割引 ・有料道路の通行料金割引 ・公共料金(NHK受信料、携帯電話料金等)の割引・減免 ・公共・民間施設(美術館、映画館等)の入場料割引 |
| 経済的な支援 | ・税金(所得税、住民税、自動車税等)の控除・減免 ・医療費の自己負担分助成(マル障など) ・各種手当(特別障害者手当など)の支給 |
| 就労に関する支援 | ・障害者雇用枠での就労 ・公的機関(ハローワーク等)による就労サポート ・民間サービス(就労移行支援、転職エージェント等)の利用 |
このように、多岐にわたるサポートが用意されています。それでは、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
日常生活の負担を軽減する支援
日々の暮らしや外出の際の負担を軽くするための、様々な割引制度が用意されています。
交通機関の運賃割引(JR・私鉄・バス・航空券など)
JRや私鉄、バス、タクシーなどの公共交通機関の運賃が割引になります。割引率は事業者や手帳の種類、介助者の同伴の有無によって異なりますが、おおむね50%の割引(本人・介助者共)となるケースが多いです。国内線の航空運賃にも割引が適用される場合があります。
公共料金等の割引・減免(NHK受信料・携帯電話料金など)
NHKの放送受信料が全額または半額免除になる制度や、各携帯電話会社が提供する基本料金の割引プランなどがあります。また、自治体によっては、水道・下水道料金の基本料金が減免される場合もあります。
公共施設・レジャー施設の入場料割引
国公立の美術館、博物館、動物園などの多くは、本人と介助者1名の入場料が無料または割引になります。さらに、映画館やテーマパークといった民間のレジャー施設でも、独自の割引制度を設けているところが増えています。
経済的な負担を軽減する支援
税金や医療費など、経済的な負担を直接的に軽減するための制度です。
税金の控除・減免(所得税・住民税・自動車税など)
所得税や住民税の計算において、「特別障害者」として扱われ、通常の障害者控除よりも大きな額の所得控除が受けられます。これにより、課税対象となる所得が減り、納税額が少なくなります。その他、相続税や贈与税の優遇、自動車税・軽自動車税の減免(条件あり)など、様々な税制上の優遇措置があります。
(参照:国税庁 No.1160 障害者控除)
医療費の助成制度(マル障など)
各自治体が設けている「心身障害者医療費助成制度(通称:マル障)」などにより、健康保険を使って病院にかかった際の、自己負担分(通常1〜3割)のほとんどが助成されます(所得制限や一部自己負担がある場合があります)。これにより、医療費の心配を大幅に減らすことができます。
各種手当(特別障害者手当など)
在宅で生活する20歳以上の、著しく重度の障害状態にある方に対して、「特別障害者手当」が支給されます(所得制限あり)。これは、障害によって生じる特別な経済的負担を軽減するための手当です。
【未来を拓く】就労に関する支援
障害者手帳は、生活の安定だけでなく、「働く」という未来を切り拓くための強力なサポートにも繋がります。
「障害者雇用枠」での就労という選択肢
一定規模以上の企業には、法律で定められた割合(法定雇用率)の障害者を雇用する義務があります。この「障害者雇用枠」の求人には、障害者手帳を持っている人のみが応募できます。この枠で採用されると、障害の特性に合わせた業務内容の調整や、通院への配慮、勤務時間の柔軟な設定といった「合理的配慮」を受けながら、安心して働き続けることが可能です。
様々な公的・民間の就労支援サービス
障害のある方の就労をサポートするための、専門的なサービスが数多く存在します。公的な機関から、より個々のニーズに合わせた民間のサービスまで、多様な選択肢があります。これについては、次の章で詳しく解説します。
【働くを考える】障害者手帳1級の方が利用できる就労支援サービス
「1級の手帳を持っていても、働くことはできるのだろうか?」その答えは、間違いなく「イエス」です。そして、その挑戦を支えるための、心強いサポーターがたくさんいます。ここでは、利用できる主な就労支援サービスをご紹介します。
まず相談したい公的な支援機関
国や自治体が運営する、無料で利用できる支援機関です。就労支援の第一歩として、まず相談してみるのが良いでしょう。
ハローワーク(専門援助部門)
全国のハローワークには、障害のある方の就職を専門にサポートする窓口があります。障害者雇用枠の求人情報の提供はもちろん、応募書類の添削や面接の練習、場合によっては面接への同行といった、きめ細やかな支援を行っています。
地域障害者職業センター
ハローワークと連携し、より専門的な職業リハビリテーションを提供する機関です。専門のカウンセラーによる職業能力の評価や、職場に適応するための支援プログラム(ジョブコーチ支援など)を受けることができます。
障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)
就職だけでなく、金銭管理や健康管理といった、働く上で基盤となる「生活面」の相談にも乗ってくれる、身近で頼れる支援機関です。雇用、福祉、医療など、様々な関係機関とのネットワークを持っています。
より専門的・実践的なサポートが受けられる民間サービス
公的機関のサポートに加え、より個々の希望やスキルに合わせた、専門性の高い民間のサービスを活用することも、成功への近道です。
就労移行支援事業所|就職準備とスキルアップを両立
一般企業への就職を目指す障害のある方が、原則2年間、無料で(※所得による条件あり)利用できる通所型の福祉サービスです。事業所に通いながら、ビジネスマナー、PCスキル、コミュニケーションスキルといった、働く上で必要な能力を高めるためのトレーニングを受けられます。また、自己分析や企業研究、職場実習などを通じて、自分に合った仕事を見つけるための、包括的なサポートが受けられるのが最大の特長です。
在宅で学べる!PCスキルや専門知識が身につくオンライン講座(Courseraなど)
就労移行支援事業所に通うのが難しい場合や、より専門的なスキルを身につけたい場合には、オンライン講座を活用するのも一つの手です。例えば、世界中の大学や企業が講座を提供するCourseraのようなプラットフォームでは、プログラミングやデータサイエンス、デジタルマーケティングといった専門分野の知識を、自分のペースで学ぶことができます。こうしたスキルは、在宅での仕事や、より専門性の高い職種を目指す上で、大きな武器となるでしょう。
障害者向け転職エージェント|非公開求人や専門的なキャリア相談
障害者雇用を専門とする転職エージェントは、障害への深い理解と、企業との強いネットワークを持つ、就職・転職活動のプロフェッショナルです。専門のキャリアアドバイザーが、あなたの経験やスキル、そして障害特性を丁寧にヒアリングし、あなたに最適な求人を提案してくれます。一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有していることも多く、一人で活動するよりも、選択肢が大きく広がる可能性があります。
スキルを活かして働く|クラウドソーシングでの副業(ココナラなど)
すぐに企業で働くのが難しい場合でも、自分のスキルや知識を活かして収入を得る方法があります。ココナラのようなスキルマーケット(クラウドソーシングサービス)では、ロゴデザイン、記事作成、データ入力、悩み相談など、自分の得意なことをサービスとして出品し、在宅で仕事を請負うことができます。まずはこうした形で実績を積み、自信をつけていくのも良いでしょう。
障害者手帳を取得するメリットと申請方法
これまでの情報を踏まえ、改めて手帳を取得するメリットと、そのための具体的な手順を確認しておきましょう。
メリットの再確認|経済的・就労・心理的な安定
障害者手帳を取得するメリットは、単に割引が受けられることだけではありません。
- 経済的な安定:各種割引や税制優遇、医療費助成、手当などにより、生活コストを抑え、経済的な基盤を安定させることができます。
- 就労機会の拡大:障害者雇用枠という、配慮を受けながら働ける選択肢が生まれ、専門的な就労支援サービスを利用することで、自分に合った仕事を見つけやすくなります。
- 心理的な安心感:「自分は公的な支援を受けられる存在である」という認識は、社会的な孤立を防ぎ、いざという時に頼れる場所があるという、大きな心理的な安心感に繋がります。
障害者手帳の申請から交付までの流れ
申請の基本的な流れは、どの手帳でも概ね同じです。
- ステップ1:主治医への相談
まずは、かかりつけの医師に、手帳の取得を考えていることを相談します。 - ステップ2:診断書・意見書の取得
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で申請書類一式をもらい、その中にある指定様式の診断書・意見書を主治医に作成してもらいます。 - ステップ3:窓口での申請
診断書・意見書、申請書、マイナンバーカード、顔写真など、必要な書類を揃えて、再度、市区町村の窓口で申請手続きを行います。 - ステップ4:審査・交付
提出された書類に基づき、専門機関で審査が行われ、等級が決定されます。その後、手帳が交付されるまで、通常1〜2ヶ月程度の期間がかかります。
自治体によって必要書類や手続きの詳細が異なる場合があるため、まずはお住まいの地域の障害福祉担当窓口に問い合わせてみることが確実です。
まとめ
この記事では、「障害者手帳1級」をテーマに、その定義から、受けられる支援、そして就労を考える上で利用できるサービスまで、網羅的に解説してきました。
1級の対象となる方は、非常に多くの手厚いサポートを受けられることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。
最後に、この記事の要点を改めて確認しましょう。
- 1級の定義
身体・精神・療育の各種手帳において、日常生活に極めて著しい制限があり、常時または多くの場面で支援を必要とする、最も重い等級です。 - 受けられる支援
交通機関や公共料金の割引、税金の控除、医療費の助成など、生活・経済の両面で幅広い支援が用意されています。 - 就労支援の選択肢
ハローワークなどの公的機関に加え、就職準備を行う「就労移行支援事業所」や、専門的なサポートが受けられる「障害者向け転職エージェント」といった、多様な選択肢があります。 - 申請方法
まずは主治医に相談し、診断書を作成してもらった上で、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で申請手続きを行います。
障害者手帳は、決して特別なものではなく、あなたらしい生活を送り、社会に参加するための、大切なパスポートです。
特に「働く」ことに関しては、一人で悩まず、専門家の力を借りることが、より良い未来への一番の近道となります。
もし、あなたがご自身のキャリアについて少しでも考え始めたなら、あるいはご家族の就労について何かヒントを探しているなら、ぜひ一度、就労移行支援事業所の見学や、障害者向け転職エージェントの無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
きっと、あなたに合った新しい道が見つかるはずです。
参考文献・出典元リスト
この記事で解説した障害者手帳に関する制度や基準は、主に厚生労働省や各自治体の公的な情報に基づいています。より詳細な一次情報を確認したい方は、以下の情報源もご参照ください。
- 厚生労働省「障害者手帳について」
各種障害者手帳の制度概要や、関連する法律について、国の公式な情報を確認できます。
(参照:厚生労働省公式サイト) - 国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」
障害者控除など、税制上の優遇措置に関する詳細な情報を確認できます。
(参照:国税庁公式サイト No.1160 障害者控除) - お住まいの都道府県・市区町村のウェブサイト
医療費助成制度や、公共料金の割引、療育手帳の等級区分など、自治体ごとに異なるサービスの詳細については、お住まいの自治体の「障害福祉」関連ページで確認するのが最も確実です。
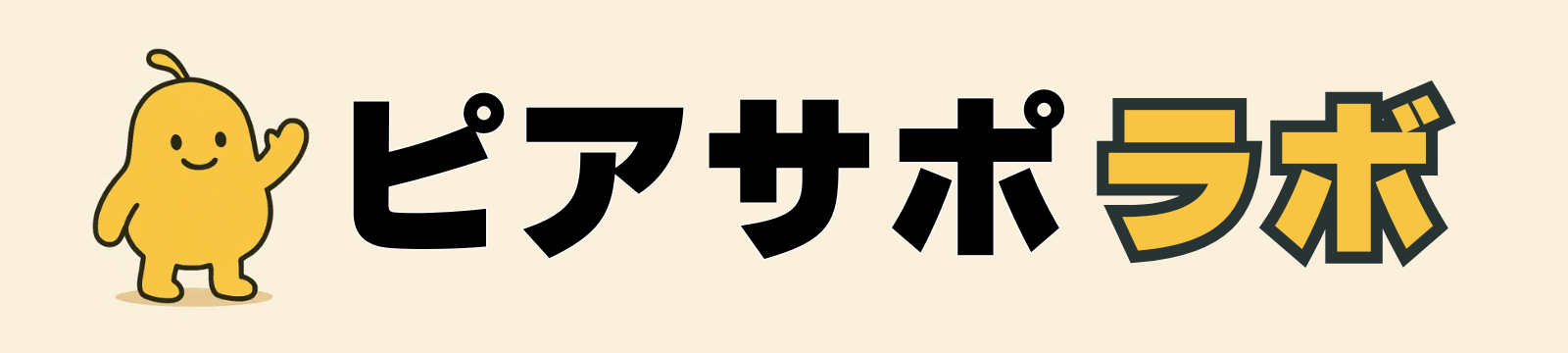




とは?目的・事例・探し方を知ろう!|一人じゃないと思える場があります-300x169.jpg)



