 ひとりやん
ひとりやん「最近『インクルーシブ』という言葉をよく聞くけど、正直、正しく意味を理解できてない……」



「ダイバーシティと何が違うの?と聞かれて、自信を持って説明できないかも?」
もし、あなたが少しでもドキッとしたなら、この記事はきっと役に立つはず!



「インクルーシブ」は、もはや単なる流行り言葉ではありません。多様化する現代社会を理解し、より良い組織やコミュニティを築くための、私たち全員にとって不可欠な考え方なのです。
この記事の目的は、難しい専門用語を並べることではありません。
「インクルーシブ」という、少し掴みどころのない概念を、誰もが知っている例え話や、職場・学校といった身近なシーンに落とし込んで、あなたの「なるほど!」を引き出すことです。
本質を理解し、自信を持って語り、そして日々の行動に活かすことができるよう、一緒に学んでいきましょう!
インクルーシブとは?|結論:「多様性を“活かす”」という考え方と行動
「インクルーシブ」という言葉の核心に迫るために、まずその言葉が持つ本来の意味と、それが目指す状態について解説します。
インクルーシブ(Inclusive)の基本的な意味|「包括的な」「すべてを含んだ」
インクルーシブ(Inclusive)とは、「すべてを含んだ」「包括的な」という意味を持つ英単語です。その名詞形である「インクルージョン(Inclusion)」は「包括」「包含」と訳され、ビジネスや社会の文脈では、すべての人々が尊重され、その一員として認められている状態を指します。
つまり、「インクルーシブな社会」や「インクルーシブな職場」とは、年齢、性別、国籍、文化、障害の有無、性的指向といった、様々な違いを持つ人々が、誰一人として排除されることなく、構成員として共に存在している社会や職場のことを言うのです。


ただ「いる」だけじゃない|一人ひとりの個性を尊重し、能力を発揮できる状態
しかし、インクルーシブの本質は、ただ多様な人々が「そこにいる」という状態だけを指すのではありません。より重要なのは、そこにいる一人ひとりの持つ違いや個性が「尊重」され、それぞれの能力や経験が十分に「発揮」され、組織や社会の意思決定に「参加」できている状態を意味します。
多様な人々がただ集まっているだけでは、少数派(マイノリティ)の声はかき消され、結局は多数派(マジョリティ)の意見だけで物事が進んでしまいます。そうではなく、全員が安心して自分らしくいられ、その違いを組織の力として活かせる仕組みや働きかけ。それこそが、「インクルーシブ」という言葉が持つ、真の意味なのです。
【最重要】インクルーシブとダイバーシティの決定的違い|図解と例えで徹底解説
「インクルーシブ」を理解する上で、最大の関門であり、最も重要なのが「ダイバーシティとの違い」です。この2つはよくセットで語られますが、その意味は全く異なります。この違いを、世界で最も有名な例え話で、あなたの頭の中にスッキリとインストールしましょう。
ダイバーシティは「状態」、インクルーシブは「行動・プロセス」
結論から言えば、両者の決定的な違いは、
- ダイバーシティは「多様な人々がいる」という“状態”を指す
- インクルーシブはその多様性を「活かす」ための“行動”や“プロセス”を指す
という点にあります。
ダイバーシティは、いわば様々な種類のタネを持っている状態。インクルーシブは、そのタネを蒔き、水をやり、それぞれの花がきれいに咲くように世話をすること、と言えるかもしれません。タネがあるだけでは、美しい花畑は生まれないのです。
有名な例え話:「パーティーに招待されるのがD、ダンスに誘われるのがI」
この違いを直感的に理解するために、ダイバーシティ&インクルージョン分野のコンサルタントであるヴァーナ・マイヤーズ氏が提唱した、非常に有名な例え話があります。
Diversity is being invited to the party.
Inclusion is being asked to dance.(ダイバーシティは、パーティーに招待されること。
インクルージョンは、そのパーティーでダンスに誘われること。)
この言葉の意味を紐解いてみましょう。
- ダイバーシティ(パーティーに招待される)
パーティー会場に、様々な年齢、国籍、性別の人々が集まっている状態。見た目はとても華やかです。しかし、ただ招待されただけで、会場の隅でポツンと一人で立っている人がいるかもしれません。
これが「ダイバーシティはあるが、インクルーシブではない」状態です。 - インクルーシブ(ダンスに誘われる)
パーティーの主催者や他の参加者が、隅にいる人に「一緒に踊りませんか?」と声をかけ、輪の中に迎え入れ、その人が楽しく踊れるように配慮すること。
これにより、招待された全ての人が、パーティーの当事者として楽しむことができます。
これが「インクルーシブな状態」です。
もう一つの例え話:様々な食材(D)と、美味しいカレー(I)
料理に例えるなら、こうも言えるでしょう。
- ダイバーシティ
冷蔵庫に、肉、魚、様々な種類の野菜、スパイスといった、多種多様な食材が揃っている状態です。可能性は無限大ですが、ただそこにあるだけです。 - インクルーシブ
シェフが、それぞれの食材の特性(ジャガイモは煮崩れやすい、スパイスは香りが強いなど)を深く理解し、適切な調理法で、それぞれの持ち味を最大限に引き出しながら、見事に調和させて、一皿の絶品カレーを完成させること。
違いと関係性が一目でわかる比較表
これまでの内容を、比較表で整理してみましょう。
| 観点 | ダイバーシティ(Diversity) | インクルーシブ(Inclusive) |
|---|---|---|
| 日本語訳 | 多様性 | 包括性、包摂性 |
| 性質 | 組織や集団の「状態」 | 組織や集団の「行動」「プロセス」「文化」 |
| 焦点 | 個々の「違い」そのもの | 「違い」をどう受け入れ、活かすか |
| 一言でいうと | 様々な人が「いる」こと | 様々な人が「活かされている」こと |



似た概念のダイバーシティとインクルーシブの違いはこれでばっちりです
なぜ今、インクルーシブが重要なのか?|企業と社会にもたらす3つのメリット
では、なぜ今、これほどまでに多くの企業や組織が「インクルーシブ」を重要視するのでしょうか。それは、倫理的に正しいというだけでなく、組織の存続と成長に不可欠な、具体的なメリットがあるからです。
メリット1:イノベーションの創出|多様な意見が化学反応を起こす
同じような背景を持つ人々が集まると、発想は均質化し、新しいアイデアは生まれにくくなります。しかし、性別、年齢、文化、経験などが異なる多様な人材が集まり、それぞれの意見が尊重され、自由に発言できる「インクルーシブな環境」があれば、そこではじめて化学反応が起こります。
自分では思いもよらなかった視点や、常識を疑うような意見がぶつかり合うことで、これまでにない革新的な製品やサービス、いわゆるイノベーションが生まれる土壌となるのです。
メリット2:人材の確保と定着|「心理的安全性」とエンゲージメントの向上
優秀な人材ほど、自分が自分らしくいられ、正当に評価される環境を求めます。従業員が「この組織では、ありのままの自分でいて大丈夫だ」と感じられる状態を、「心理的安全性」と呼びます。インクルーシブな職場は、この心理的安全性が非常に高いのが特徴です。
心理的安全性が高い職場では、従業員は安心して挑戦し、能力を最大限に発揮できます。結果として、組織への愛着や貢献意欲であるエンゲージメントが高まり、優秀な人材の離職を防ぐとともに、新たな人材を惹きつける魅力的な職場となるのです。
メリット3:企業の持続的成長|顧客ニーズの多様化とブランドイメージ
現代の市場は、顧客のニーズも極めて多様化しています。多様な従業員を抱えるインクルーシブな企業は、この多様な顧客ニーズを、より深く、正確に理解することができます。結果として、顧客に本当に響く製品やサービスを開発し、ビジネスを成長させることができるのです。
また、インクルーシブな姿勢を明確にすることは、企業の社会的評価を高め、顧客や投資家からの信頼を獲得する上でも、非常に重要な要素となっています。
【シーン別】インクルーシブな社会の具体例
「インクルーシブ」という概念が、私たちの身近な場面でどのように実践されるのか、具体的なシーンを思い浮かべてみましょう。ここでは、「職場」「教育」「デザイン」という3つの切り口で、その姿を覗いてみます。
インクルーシブな「職場」とは?
インクルーシブな職場とは、多様な従業員が、その能力を最大限に発揮できる場所です。そこでは、以下のような工夫が見られます。
会議での工夫|全員が発言しやすい環境づくり
声の大きい人の意見ばかりが通るのではなく、会議の進行役(ファシリテーター)が、普段あまり発言しない人や、若手社員、異なる部署のメンバーにも意識的に話を振ります。「〇〇さんは、この点についてどう思いますか?」と問いかけることで、多様な視点を引き出し、意思決定の質を高めます。
評価制度|多様な価値観を認める仕組み
画一的な評価基準ではなく、従業員一人ひとりの持つ異なる強みや、貢献の仕方を多角的に評価する仕組みを取り入れています。例えば、育児中の時短勤務社員に対して、労働時間の長短ではなく、その時間内で達成した成果や、チームへの貢献度を正当に評価します。
働き方|柔軟な勤務形態とコミュニケーション
リモートワークやフレックスタイム制など、個々の従業員のライフステージや価値観に合わせた、柔軟な働き方を許容します。また、社内チャットツールなどで、部署や役職を越えて、誰もが気軽に意見を発信できるオープンなコミュニケーション文化が醸成されています。
インクルーシブな「教育・保育」とは?
インクルーシブ教育(インクルーシブ教育システム)とは、障害のある子どもと、ない子どもが、同じ場で共に学ぶことを基本とする考え方です。これは、単に同じ教室にいる、というだけではありません。
障害のある子も、ない子も、共に学ぶ環境
障害の有無によって学ぶ場を分けるのではなく、可能な限り同じ教室で、すべての子どもが共に学ぶことを目指します。これにより、子どもたちは幼い頃から、多様な他者の存在を自然なものとして受け入れ、互いを尊重する心を育むことができます。
一人ひとりの特性に合わせた学びのサポート
インクルーシブ教育の核心は、集団の学習ペースに個人を合わせさせるのではなく、一人ひとりの教育的ニーズに合わせて、学びの環境を調整することにあります。例えば、文字を読むのが苦手な子にはタブレット端末の使用を許可したり、車いすの子が参加しやすいように体育のルールを工夫したりと、個別の合理的配慮が行われます。
インクルーシブな「デザイン」とは?
製品やサービス開発の世界でも、インクルーシブな視点は不可欠です。
製品・サービス開発におけるインクルーシブデザイン
これは、これまで「平均的なユーザー」像から排除されてきた人々(例:障害のある方、特定の身体特性を持つ方)を、デザインプロセスの初期段階から「専門家」として巻き込み、共に製品やサービスを創り上げていくアプローチです。このプロセスから、誰もが予想しなかった革新的な製品が生まれることがあります。
インクルーシブデザインについては、以下の記事で詳しく説明しています。
||準備中||
街づくりにおけるユニバーサルデザイン
誰もが暮らしやすい街を作る「ユニバーサルデザイン」も、インクルーシブな社会を実現するための重要なデザインアプローチです。例えば、ノンステップバスや、誰でも使いやすい多機能トイレは、特定の人のためだけでなく、結果として多くの人々の利便性を高めています。
ユニバーサルデザインについては、以下の記事で詳しく説明しています。
「インクルーシブ」は、もはや単なる流行り言葉ではありません。多様化する現代社会を理解し、より良い組織やコミュニティを築くための、私たち全員にとって不可欠な考え方なのです。
||準備中||
【発展編】DE&I、そしてビロンギングへ|進化する概念を理解する
「インクルーシブ」の理解をさらに深めるために、近年主流となっている、より発展的な概念についても触れておきましょう。これらの言葉を知ることで、あなたは時代の最先端の議論についていくことができます。
DE&Iとは?|「E=エクイティ(Equity)」の重要性
最近、企業理念などで「DE&Iの推進」という言葉を目にすることが増えました。これは、D(ダイバーシティ)、E(エクイティ)、I(インクルージョン)の頭文字を取ったものです。
エクイティ(Equity)とイコーリティ(Equality)の違い
エクイティ(Equity)は「公平性」と訳されます。これは、よく似た言葉であるイコーリティ(Equality)=「平等」とは、意味が異なります。
- イコーリティ(平等):全員に、全く同じものを与えること。例えば、身長の違う3人に、同じ高さの台を一つずつ与えるようなものです。
- エクイティ(公平性):一人ひとりの状況や特性の違いを考慮し、それぞれに必要なサポートを提供することで、結果として全員が同じスタートラインに立てるようにすること。例えば、身長の違う3人に、それぞれ異なる高さの台を与え、全員が同じ高さから景色を見られるようにすることです。
つまり、ただ多様な人々を集め(D)、活躍の機会を与える(I)だけでなく、その前提として、そもそもスタートラインが不公平になっていないかを見直し、必要な支援を行う(E)ことの重要性が、DE&Iという言葉には込められているのです。
インクルージョンの先にある「ビロンギング(Belonging)」とは?
そして、DE&Iが実現された結果として生まれる、究極の状態。それが「ビロンギング(Belonging)」です。
「ここに居ていいんだ」という、心からの帰属意識
ビロンギングは「帰属意識」と訳されます。これは、組織にいる一人ひとりが、「自分は、ありのままの自分で、このチームの一員として受け入れられている」と、心から安心して感じられる状態を指します。
ダンスに誘われ(インクルージョン)、輪の中で楽しく踊った結果、「このパーティー、最高!自分はこの場にいていいんだ!」と感じること。この心理的な繋がりこそが、人々のパフォーマンスを最大化させ、組織を本当に強くする源泉となると考えられています。
D・E・I・Bの関係性の全体像
これらの概念の関係性を図で表すとすると以下のようになります。
エクイティ(公平性)という土台の上に、ダイバーシティ(多様性)という状態があり、そこにインクルージョン(包括)という働きかけを行うことで、最終的にビロンギング(帰属意識)という最高の状態が生まれる。
このように、各概念は連動し、進化していくのです。
まとめ
この記事では、「インクルーシブとは何か」をテーマに、その核心的な意味から、ダイバーシティとの明確な違い、具体的な事例、そして未来に向けた発展的な概念まで、網羅的に解説してきました。
「インクルーシブ」という言葉が、あなたの中で、もっと具体的で、もっと自分事として感じられるようになったのではないでしょうか。
最後に、この記事の要点を改めて確認し、明日からのあなたの視点と行動を変える力にしてください。
- インクルーシブの核心
多様な人々がただ「存在する」だけでなく、その一人ひとりの個性や能力が尊重され、十分に「活かされている」状態や、そのための行動を指します。 - ダイバーシティとの違い
「パーティーに招待される(多様な人が集まっている状態)」のがダイバーシティ。「ダンスに誘われる(その場で活躍できる)」のがインクルーシブです。状態と行動という、明確な違いがあります。 - 重要な理由とメリット
多様な意見の化学反応によるイノベーションの創出や、従業員のエンゲージメント向上など、企業や組織の持続的な成長に不可欠な要素です。 - 身近な具体例
会議で全員に発言を促したり、一人ひとりの学び方に合わせたりと、インクルーシブな考え方は、職場や教育といった、私たちのすぐそばにある場面で実践できます。 - 進化する概念「DE&I」
近年では、機会の公平性を保証する「エクイティ(E)」の重要性が増しており、「DE&I」として語られるのが主流になっています。
インクルーシブな社会や組織を築くことは、一朝一夕にできることではありません。しかし、私たち一人ひとりが、この「インclusーブ」というレンズを通して世界を見る意識を持つことから、変化は始まります。
今日の学びが、あなたのチームやコミュニティを、そしてあなた自身を、より豊かで、より創造的な未来へと導く、確かな一歩となることを心から願っています。
参考文献・出典元リスト
本記事で解説したインクルーシブやDE&Iに関する概念は、多くの研究機関やコンサルティングファームによって議論・発信されています。より深く学びたい方は、以下の情報源もご参照ください。
- ハーバード・ビジネス・レビュー(Harvard Business Review)
DE&Iに関する経営学的な論文や調査レポートが多数掲載されています。企業のメリットなどをデータで確認したい場合に有益です。
(参照:「HBR DE&I」などで検索) - 内閣府「男女共同参画局」
日本政府の視点から、ダイバーシティやインクルージョンの推進に関する方針やデータを確認できます。
(参照:男女共同参画局 公式サイト) - 各種人事・組織コンサルティングファームのレポート
デロイト トーマツ グループやPwCなどの企業は、DE&Iに関する最新の調査レポートや考察を定期的に公開しており、企業の具体的な取り組み事例を知る上で参考になります。
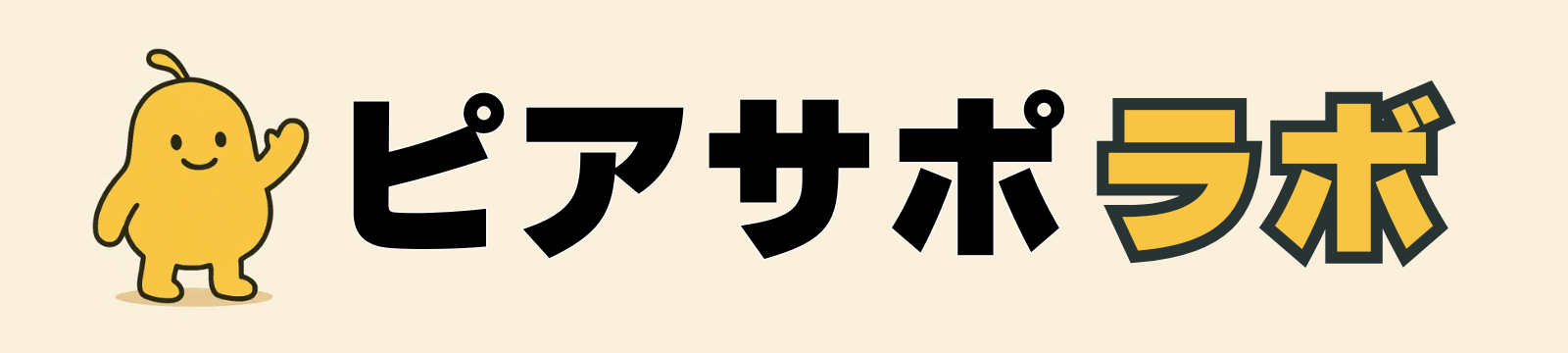






とは?目的・事例・探し方を知ろう!|一人じゃないと思える場があります-300x169.jpg)
