 ひとりやん
ひとりやんこの悩み、誰にも分かってもらえないんだよね……



世界でたった一人、自分だけがおかしいんじゃないかな……?
出口の見えない暗闇の中で、今、あなたはそんな風に感じているかもしれません。
そんな時、ふと目にした「当事者会」という言葉。
もしかしたら、そこには自分と同じ境遇の人がいるかもしれない、という淡い希望。と同時に、「知らない場所に行くのは怖い」「自分の話を否定されたらどうしよう」という、大きな不安。



その気持ち、痛いほどよくわかります。
大丈夫です。この記事では、そんな皆さんの「当事者会」への期待を確かなものにし、不安を和らげられるよう、わかりやすく解説していきます!
当事者会は、決して怖い場所ではありません。
それは、あなたが「一人じゃない」と心から実感できる、温かくて安全な「居場所」なのです。


当事者会(自助グループ)とは?|同じ悩みを持つ仲間と繋がる場所
当事者会の世界に触れる前に、まずその基本的な目的や、参加することで得られるメリットについて見ていきましょう。



当事者会のような場が、皆さんにとってどのような価値を持つ可能性があるのかを知ることが最初の一歩です!
基本的な目的|分かち合い、支え合い、そして回復へ
当事者会とは、一言で言えば病気、障害、依存症、あるいは特定のライフイベント(例:死別、不登校など)といった、同じ悩みや経験を持つ「当事者」同士が集まり、自らの体験や想いを自由に語り合う場所です。
その最大の目的は、互いの経験を「分かち合い」、そのプロセスを通じてお互いを「支え合い」、そして最終的には一人ひとりが自分の力で「回復」していくことを後押しすることにあります。
専門家が運営する治療プログラムとは異なり、あくまで当事者が主体となって運営されるのが特徴で、「自助グループ(セルフヘルプ・グループ)」とも呼ばれます。


参加する3つの大きなメリット
当事者会に参加することは、多くの人にとって、医療やカウンセリングとはまた違う、非常に大きな価値をもたらします。
代表的なメリットは以下の3つ。
それでは、詳しくみていきましょう!
メリット1:孤立感の解消と、心からの安心感
「こんなことで苦しんでいるのは、自分だけだ」。その孤独感こそが、何よりも心を苛みます。当事者会に行けば、自分と全く同じことで悩み、涙を流している仲間がいます。その存在を知るだけで、「ああ、一人じゃなかったんだ」という、心からの安堵感に包まれます。
メリット2:リアルな情報交換と、新しい視点の獲得
当事者会は、本やインターネットには載っていない、生きた情報に触れられる貴重な機会です。
「この制度を使うと便利だよ」
「こういう時は、こうやって乗り切っているよ」
そういった、先輩当事者のリアルな生活の知恵や工夫は、明日からすぐに役立つ実践的な情報です。
メリット3:自己肯定感の回復と、エンパワメント
自分の体験談を、誰にも否定されずに聞いてもらえる。そして、時には自分の経験が、他の誰かの役に立つ。
この経験は、「自分は、そのままで価値があるんだ」という自己肯定感を取り戻させてくれます。
家族会との違いは?
当事者会とよく似たものに「家族会」があります。これは、当事者本人ではなく、その家族(親、配偶者、きょうだいなど)が集まる会です。家族ならではの悩みや葛藤を分かち合い、支え合うことを目的としており、当事者会と同様に、多くの方にとって重要な支えとなっています。会によっては、当事者と家族が一緒に参加する場合もあります。
当事者会では何をするの?|主な活動内容と基本的な流れ



実際に参加したら、一体どんなことをするんだろう?
そんな疑問は当然出てきます。会の種類によってさまざまですが、多くの当事者会で中心となる活動をご紹介します。
基本は「ミーティング」|車座になって語り合う
当事者会の基本スタイルは、数人から十数人が輪になって座り、順番に自分の想いや体験を語り合う「ミーティング(分かち合いの場)」です。
公民館の多目的室や貸し会議室のような場所で開催されることもあれば、カフェや古民家のような場所で行われることも。
司会進行役がいますが、偉い先生がいるわけではありません。参加者は皆、対等な立場の「仲間」です。
時間は1時間半から2時間程度が一般的で、最初にその会のルールを確認し、その後、順番に一人ずつ話していきます。話す内容は、最近あったこと、今悩んでいること、過去の体験など、何でも構いません。



もちろん、話したくない時は「パスします」と言って、話さなくても大丈夫。その場にいて仲間の話に耳を傾けているだけでも、十分に意味がありますよ!
活動の例|分かち合い(言いっぱなし聞きっぱなし)、勉強会、レクリエーションなど
ミーティング(分かち合い)が最も基本的な活動ですが、会によっては、以下のような様々な活動を行っています。
- 勉強会・講演会:専門家(医師、ソーシャルワーカーなど)を招いて、病気や制度に関する勉強会を開催する。
- 当事者研究:自分自身の困難や特性について、仲間と共に分析・研究し、ユニークな対処法を見つけていく。
- レクリエーション:バーベキューやお茶会、スポーツなど、語り合いだけでなく、楽しい活動を通じて交流を深める。
- 会報の発行やオンラインでの交流:会の活動を報告する会報を作成したり、SNSやオンライン会議ツールを使って、ミーティング以外の時間でも交流したりする。
【最重要】当事者会に安心して参加するために|参加が怖い、不安な方必見
ここまで読んで、



少し興味は湧いてきたけど、やっぱり知らない場所に行くのは怖い……
そう感じている方も多いでしょう。その気持ちは、とても自然なことです。ここでは、そんなあなたの不安を和らげるために、ほとんどの当事者会で大切にされている「安心して参加するしてもらうためのルール」について解説します。
当事者会や参加者を守るための大切な「3つのルール」
多くの当事者会では、参加者全員が安心して自分のことを話せるように、いくつかのグラウンドルールを設けています。その中でも、特に重要なのが以下の3つです。
ルール1:言いっぱなし・聞きっぱなし|批判NG、アドバイスNG
当事者会の最も特徴的で、最も大切なルールは「批判NG、アドバイスNG」です。誰かが話している間、他の人は批評や評価、そして安易なアドバイスをせず、ただ静かにその話に耳を傾けます。
なぜなら、この場所は議論をして結論を出す場ではないからです。
「こうした方がいいよ」というアドバイスは、時に「今のあなたは間違っている」というメッセージになり、相手を傷つけることがあります。
ルール2:秘密厳守|会で見聞きしたことは、決して外に漏らさない
会で語られるのは、非常にプライベートで、デリケートな内容です。参加者は、「ここで話されたことは、この場限りのものとする」という、絶対的な秘密厳守のルールを守る義務があります。
ルール3:匿名での参加(ニックネームOK)
多くの当事者会では、本名を名乗る必要はありません。ニックネームや、下の名前だけで参加することができます。
また、所属(会社や学校など)や、詳しい居住地などを話す必要もありません。あなたが「話したい」と思う範囲のことだけを話せば良いのです。
【注意!】会の「雰囲気」は、それぞれ違う
当事者会と一言で言っても、その雰囲気は会によって様々です。真剣に語り合う静かな会もあれば、笑いの絶えない和気あいあいとした会もあります。また、メンバーの年齢層や、会の歴史の長さによってもカラーは異なります。
もし最初に参加した会が「自分には合わないな」と感じても、どうか「当事者会はダメだ」と諦めないでください。あなたにぴったりの「居場所」が、きっとどこかにあるはずです。
もし合わないと感じたら|無理せず、途中で帰っても大丈夫
これも非常に重要なことです。もし、参加してみて、その場の雰囲気が合わなかったり、話を聞いているのが辛くなったりしたら、あなたはいつでも、理由を告げずに、黙って席を立って帰って構いません。
誰も、あなたを責めたり、引き止めたりはしません。あなたの心と体の安全が、何よりも最優先されるべきだからです。参加するもしないも、居続けるも帰るも、すべてはあなたの自由です。そのことを、どうか忘れないでください。
【実践編】自分に合った当事者会・自助グループの探し方
「少し、勇気を出してみようかな」。そう感じた方のために、自分に合った当事者会や自助グループを見つけるための、具体的な方法をご紹介します。扉は、一つではありません。
探し方1:インターネットの検索サイトや一覧サイトを利用する
最も手軽なのは、インターネットで探す方法です。「NPO法人 全国自助グループ・情報センター」のように、全国の自助グループの情報をまとめたポータルサイトがあります。
また、「(お住まいの地域名)(あなたの悩み)当事者会/自助グループ 」といったキーワードで検索すると、地域の会が見つかる可能性が高いです。
探し方2:お住まいの地域の行政窓口に問い合わせる
市区町村の役所や、地域の保健所なども、管轄内の当事者会・家族会の情報を把握していることが多いです。どこに相談すればいいか分からない場合は、まずここから始めてみるのが確実です。
市区町村の障害福祉課、保健所、精神保健福祉センターなど
お住まいの市区町村のウェブサイトで、「障害福祉担当」や「保健センター」といった部署を探し、電話やメールで問い合わせてみましょう。
「〇〇に関する当事者会や家族会の情報を知りたいのですが」と伝えれば、担当者が情報を提供してくれたり、適切な相談先を教えてくれたりします。
探し方3:病院やクリニックなどの医療機関で紹介してもらう
もし、あなたが特定の病気や障害で通院している場合、かかりつけの医師や、院内にいる医療ソーシャルワーカーに相談してみるのも非常に有効な方法です。
彼らは、地域の患者会や家族会と連携していることが多く、あなたの状況に合った会を紹介してくれる可能性があります。
まずは「オンライン当事者会」から参加してみるのも一つの手
「いきなり対面の会に行くのは、まだハードルが高い…」。そんな方には、オンライン当事者会がおすすめです。Zoomなどのビデオ会議ツールを使い、自宅から、顔を出さずに(音声だけでも)参加できる会が、近年急速に増えています。
移動の負担がなく、より匿名性が高いオンラインの会で、まずは当事者会の雰囲気を体験してみる。それは、次の一歩に向けた、とても賢明で、優しい選択です。
【発展編】自分で当事者会を立ち上げたいと思ったら
もし、あなたが自分の地域や悩みに合う会を見つけられなかった場合、「それなら、自分で作ってしまおう」という選択肢もあります。それは、非常に勇気と力のある、素晴らしいアクションです。
仲間集めから、場所の確保、ルールの設定まで
当事者会を立ち上げるのに、特別な資格は必要ありません。まずは、同じ思いを持つ仲間をSNSなどで探し、数人で集まって話すことから始めます。
場所は、地域の公民館やコミュニティセンターの会議室などを、安価で借りることができます。そして、先ほど解説したような、参加者が安心して話せるための「ルール」を、みんなで確認し合うことが重要です。
自分で会を主催してみたい場合、オンラインだと場所等の制約なくでき、遠方の似た悩みを持つ人ともつながりやすいなど、比較的気軽に出来る点がメリットですね。


運営をサポートしてくれる団体や、ファシリテーターの養成講座
とはいえ、会の運営には様々なノウハウが必要です。地域の社会福祉協議会や、NPO法人が、自助グループの立ち上げや運営をサポートしてくれる場合があります。
また、話し合いを円滑に進める進行役である「ファシリテーター」を養成するための講座なども開催されています。こうした外部の力を借りることで、より安全で、持続可能な会を運営していくことができます。
まとめ
この記事では、「当事者会とは何か」をテーマに、その目的や活動内容、そして参加への不安を和らげるための知識や、具体的な会の探し方までを解説してきました。
当事者会が、決して特別な場所ではなく、あなたと同じように悩み、それでも前を向こうとする仲間たちが集う、温かい「居場所」であることが、少しでも伝わっていれば幸いです。
最後に、この記事の最も大切なポイントを、もう一度心に留めておいてください。
- 当事者会の目的
同じ経験を持つ仲間と繋がり、分かち合い、支え合うことで、孤立感を解消し、回復への力を得るための場所です。 - 安全を守るルール
「言いっぱなし聞きっぱなし」「秘密厳守」といった大切なルールが、誰もが安心して自分の気持ちを話せる、安全な空間を守っています。 - 参加への不安はあって当然
初めての場所に行くのは、誰でも怖いものです。話したくなければ聞いているだけでも大丈夫。合わなければ、そっと席を立っても誰も責めません。あなたのペースが、何よりも尊重されます。 - 探し方は一つじゃない
インターネット、行政の窓口、医療機関など、当事者会と繋がるための扉は、いくつも用意されています。オンラインの会から試してみるのも良いでしょう。
あなたは、決して一人ではありません。
日本中に、世界中に、あなたと同じ悩みや経験を分か-ち合える仲間がいます。
当事者会は、その仲間と出会うための、一つの扉です。
この記事が、あなたがその扉を、ほんの少しだけ開けてみるための、小さな勇気となったなら、これほど嬉しいことはありません。
参考文献・出典元リスト
当事者会や自助グループに関する情報は、様々な公的機関やNPO法人が提供しています。より詳しい情報や、お近くの会を探したい場合は、以下の情報源もご参照ください。
- NPO法人 全国自助グループ・情報センター
様々な分野の自助グループの情報を集約・発信しているNPO法人。ウェブサイトでは、グループの検索や、立ち上げに関する相談が可能です。
(参照:「全国自助グループ・情報センター」で検索) - こころの耳(厚生労働省)
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト。自助グループを含む、様々な相談窓口の情報が掲載されています。
(参照:こころの耳 公式サイト) - お住まいの市区町村・保健所のウェブサイト
地域の当事者会や家族会の情報が、イベント情報などと共に掲載されている場合があります。「〇〇市 精神保健福祉相談」などのキーワードで検索してみてください。
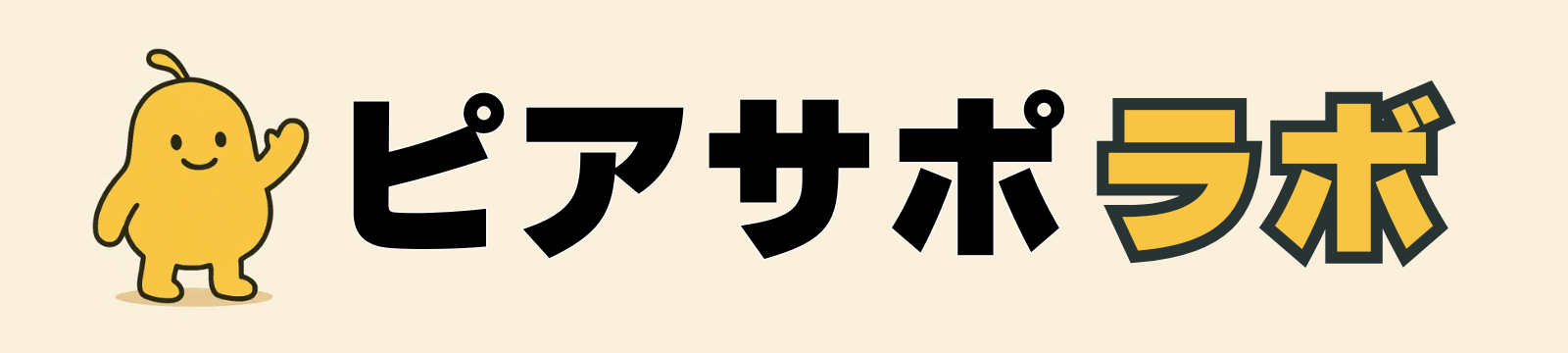
とは?目的・事例・探し方を知ろう!|一人じゃないと思える場があります.jpg)





